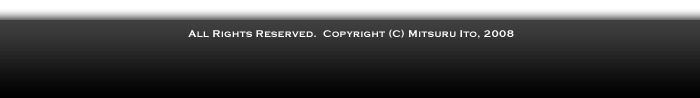| |
 |
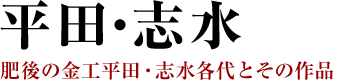 |
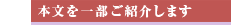 |
 |
| |
 (本文より ) (本文より )
志水甚五について
志水家は、肥後金工四主流の一つである。
初代の作品は、真鍮据文の鷹や梟の鐔があり、刀装具の世界では圧倒的な存在感を持った異色の作者として知られている。
四主流のうち、志水と西垣は平田彦三の門人であり、肥後入国のとき、細川三斎公に従って八代に住んだが、三斎逝去後、平田家も西垣家も熊本に移住しているので、八代に残ったのは志水家のみである。
松井文庫にある、寛政元年に書かれた「御町会所古記之内書抜 御巡見様御尋之御答」(添1図)の中で種々の職業を答えた中に「白金師 壹人」とある。もちろんこれは志水甚五のことである。また、「八代城郭図」(添2図)の袋町角に「志水銀太」の名がある。これは、平田彦三が三斎公から排領した「八代袋町東角屋敷口二十間八十九門三尺」と同じ所である。
現在も熊本県八代市袋町に、子孫が住んで居られ、住所は、江戸時代と変わりがない。また、四主流のうちでは最も在銘の作品が現存するばかりか、初代から五代まで個性豊かな作品を残している。
志水家の研究は肥後金工全体を知る上で、非常に重要である。
●志水各代について
肥後金工の著作、古文書としては、明治の、長屋重名翁の「肥後金工録」、西垣四郎作翁の「肥後鐔工人名調」、志水家の「先祖附」、米光太平翁蔵の古文書、井出藤九郎氏旧蔵の古文書、刀剣博物館にある「八代甚吾家鐔製作粉本」(添3図)などである。昭和に入ってからは、三十九年(1964)の「肥後金工大鑑」、六十年(1985)の熊本での展覧会の図譜である「肥後の金工」がある。部分的著作としては、「鐔大鑑」、「金工名作集」、「日本刀講座」、「刀装小道具講座」、「日本刀大鑑」、「透鐔」がある。この中で、「肥後金工録」は、長屋翁自筆原本が二種、明治三十五年(1902)の初版本、そして大正十四年(1925)の網屋版再版がある。
西垣翁の「肥後鐔工人名調」は残念ながら現在は行方不明であるが、そのほとんどの抜粋が「鐔の会」大正八年(1919)版四号に「肥後鐔及赤坂鐔に就いて」という記事の中に存在している。「肥後金工録」は、長屋翁が神吉楽寿の話を参考にして著されたもので、「肥後鐔工人名調」は、西垣家の八代目当主四郎作翁の著作である。両書の中には、かなりの相違があるので表にしてみた。 |
 |
|
|